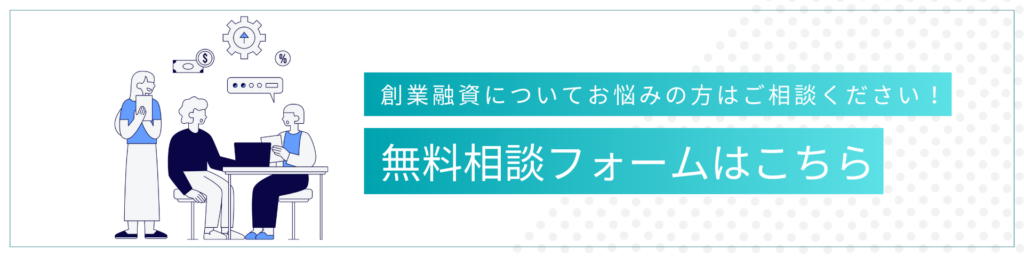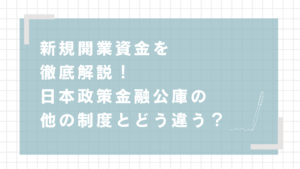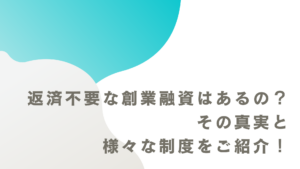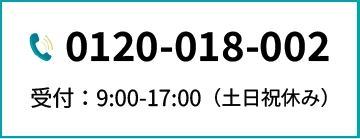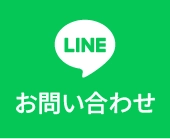日本政策金融公庫の審査は厳しい?失敗しないポイントとは
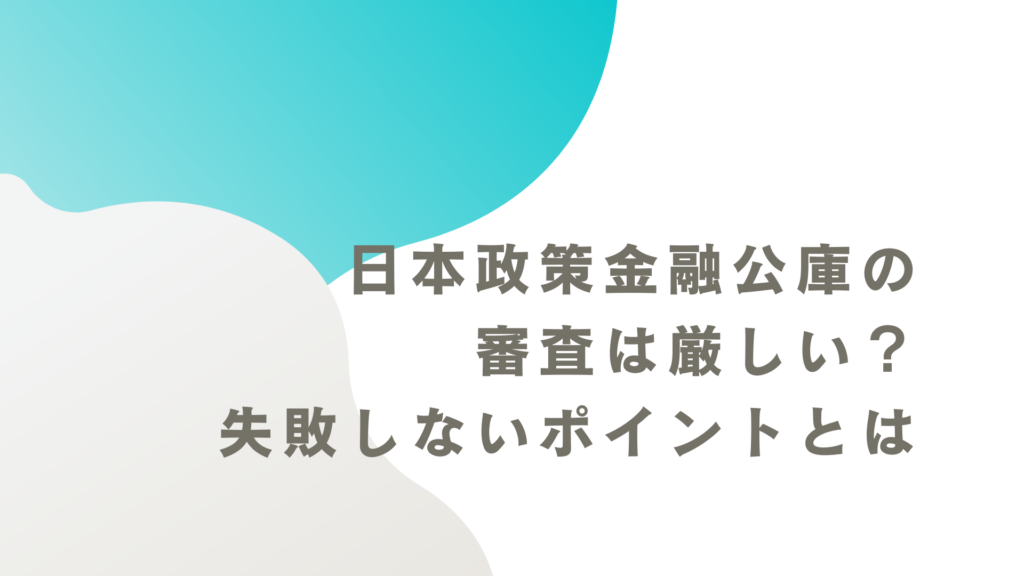
熊本で起業を検討している方が、最初に乗り越えなければならない壁は事業資金の調達です。
起業のタイミングで、すでに自己資金が充足している方もいればそうでない方もいらっしゃるでしょう。
自己資金だけで不安な方の多くは創業融資を検討しています。
その場合、国が100%出資している公的な機関である「日本政策金融公庫」の創業融資を利用する方が多いです。
日本政策金融公庫は、主に個人事業主や中小企業に対しての融資を行っており、比較的低金利で創業時にも審査が通りやすい特徴があります。
今回は、その日本政策金融公庫の審査基準はどの程度厳しいものなのかをお伝えします。
さらに、その創業融資の審査で失敗しないポイントを解説していきます。
\各種融資についてお悩みの方はご相談ください/
無料相談はこちら!
日本政策金融公庫の審査とは?
「創業融資を検討しているけれど、日本政策金融公庫の“審査”って、正直どんなものなのか分からない…」
そんな不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、これから融資を申し込もうとしている方に向けて、「日本政策金融公庫の審査とはそもそも何か?」という基本的な部分から、具体的な流れや審査の傾向まで解説していきます!
日本政策金融公庫の審査制度の特徴
日本政策金融公庫は、民間の銀行とは異なり、政府が100%出資している公的金融機関です。
つまり、利益を目的とした金融機関ではなく、中小企業や創業者を支援することが目的の組織なのです。
だからといって「誰でも簡単に融資を受けられる」というわけではありません。
公的な立場にあるからこそ、慎重に見極める「審査」をきちんと行っています。
公庫の審査は、「この事業は本当に継続していけるのか?」「返済能力はあるのか?」を中心にチェックされます。
また、銀行のように「担保」や「保証人」を重視するよりも、事業計画書の中身や本人の熱意・実現性に重点を置いている点が特徴です。
審査通過率はどれくらい?
公庫は、民間の銀行に比べれば融資のハードルが低いと言われていますが、それでも「誰でも通る」わけではありません。
そして、日本政策金融公庫は公式に通過率を公表していません。
ただ、融資支援の現場での実感や、複数の専門家による推定値としては、おおよそ50~60%程度と言われています。
つまり、2人に1人は審査に通らないということです。
特に「自己資金が少ない」「計画書があいまい」「信用情報に不安がある」などの要素がある場合は、審査で落ちる可能性が高くなってしまいます。
裏を返せば、審査のポイントをしっかり押さえて準備すれば、通過できる可能性は十分あるということ。この記事を通して、その「押さえるべきポイント」も詳しく解説していきますので、安心してくださいね。
審査期間の目安は?
融資の申し込みをしたら、どのくらいで結果が出るのかも気になるところですよね。
一般的に、日本政策金融公庫の創業融資の審査期間は、およそ2〜3週間前後とされています。
ただし、これはあくまで「書類がしっかり整っている」「面談がスムーズに終わった」など、スケジュール通りに進んだ場合の話です。
以下のようなケースでは、審査が遅れることもあります。
- 提出書類に不備がある
- 面談の日程が合わず先延ばしになった
- 担当者の確認事項が多く、再提出が必要になった
- 繁忙期(年度末や年始など)で審査が立て込んでいる
また、希望する融資額が高額な場合や、事業内容が複雑な場合も、より慎重にチェックされるため、1ヶ月以上かかることもあるのです。
融資が決定するまでには、さまざまな工程があるため、「2週間で結果が出るから、今すぐ資金調達できる」と考えるのは危険です。
あらかじめ時間に余裕を持って申し込むことをおすすめします。
審査のチェックポイントとは?
日本政策金融公庫の審査では、民間の金融機関と異なり、担保や保証人が不要な分、事業そのものの実現性や申込者の人柄、信頼性がしっかり見られます。
ここでは、公庫の審査でとくに重視されるポイントを順番にご紹介します。
創業計画書では何を見られる?
まず、審査の中心となるのが「創業計画書」です。
日本政策金融公庫には専用のフォーマットが用意されていますが、ただ記入すれば良いというものでははありません。
書かれた内容に「根拠」があるかどうかが問われます。
たとえば、
- 売上予測に現実味はあるか(市場規模、競合の状況などを踏まえているか)
- 仕入れや経費の計算が雑でないか(過不足がないか)
- 運転資金と設備資金の使い分けが明確か
- なぜこの事業を始めるのか、熱意が伝わるか
といった部分がチェックされます。
特に創業時は実績がないため、「計画の説得力」が命です。
数字に自信がない場合でも、税理士や創業支援の専門家にアドバイスを受けながら、ロジック立てて説明できるようにしておくと安心です。
自己資金はどれくらい必要?
よく質問を受けるのが、「自己資金ってどのくらいあればいいの?」という疑問です。
一般的に、公庫は創業融資の申込額の「1割以上」の自己資金を求めるとされています。
つまり、500万円を借りたいなら、少なくとも50万円以上の自己資金があるのが理想ということですね。
ただしこれは最低ライン。
実際の審査では、全体の自己資金割合が20〜30%あれば、より信頼されやすい傾向があります。
また、自己資金は「本当に自分のお金で貯めたものなのか?」という点も見られます。
たとえば、急に親から振り込まれたような入金は「見せ金」と疑われてしまう可能性も。
コツコツ貯めた履歴が通帳に残っていることが信頼につながります。
預金通帳・会計データで確認されること
日本政策金融公庫では、創業者の預金通帳を直近6ヶ月〜1年分ほど提出するよう求められます。
これは、自己資金の出どころを確認するためでもありますが、ほかにも以下のような点を見ています。
- 収入や支出のバランスは整っているか
- ギャンブルや高額な浪費の履歴がないか
- 水道光熱費や税金の滞納がないか
通帳の中身は、「あなたの生活やお金の使い方」を映し出す鏡です。
日頃から記録を残し、きちんとしたお金の使い方をしていることが大切です。
また、すでに開業している場合は、会計ソフトのデータや試算表の提出も求められることがあります。
帳簿がきちんとつけられているかも、審査での信頼度アップに直結しますよ。
他社借入・返済履歴と信用情報チェックの実態
審査では、あなたの「信用情報」もチェックされます。
これは、これまでに借金をきちんと返してきたか、延滞はなかったか、といった金融履歴を記録するデータベースです。
日本政策金融公庫が照会する主な機関は以下の通りです。
- CIC(株式会社シー・アイ・シー):クレジットカードやローンの履歴
- JICC(日本信用情報機構):消費者金融や携帯電話の割賦払いなど
- 全国銀行個人信用情報センター:銀行系ローンや住宅ローン
たとえば、過去に長期延滞や債務整理があると、「返済能力に不安あり」と判断されてしまいます。
逆に、クレジットカードをきちんと利用・返済してきた人は「信用できる」と評価されることも。
「携帯代の分割払いを滞納してブラックリストに載っていた…」という例もあるため、心配な方は一度、自分の信用情報を照会して確認しておくことをおすすめします。
面談で好印象を与えるポイント
書類審査を通過すると、次に待っているのが「面談」です。
この面談では、事業の実現性やあなたの熱意、人柄などが総合的にチェックされます。
印象を良くするために意識しておきたいポイントは以下の通りです。
- 創業の理由を、自分の言葉で説明できるようにしておく
- 計画書の内容をよく理解し、数字に自信を持って話せるようにする
- 服装や態度は「社会人としての常識」を意識する
- 嘘をつかない、背伸びをしない(ありのままを丁寧に伝える!)
公庫の担当者は、「この人が事業をちゃんと継続できるか」を人として見ています。
専門用語を知らなくても、誠実で熱意が伝わる話し方ができれば、それだけで大きなプラス評価になることもあるのです。
申し込み~結果通知の流れを解説!
「審査が重要なのは分かったけど、実際にどうやって申し込めばいいの?」
そんな疑問をお持ちの方も多いと思います。
次に、日本政策金融公庫で創業融資を申し込んでから、審査結果が通知されるまでの流れを解説していきます。
①まずは事前相談から!
まず最初におすすめしたいのが、「事前相談」です。
日本公庫では、申し込み前に無料で相談が可能です。
最寄りの支店に電話をかけて予約を取るのが一般的ですが、最近ではインターネット経由でWeb面談の予約も可能になっています。
相談では、以下のようなことを確認してもらえます。
- 融資の対象になるか
- 必要な書類や準備物
- 自己資金や計画書の不安点
- スケジュールや注意点
「本当に借りられるか不安…」という方ほど、事前に相談しておくことで、無駄な時間や手間を省けます。
また、創業融資のサポートをしている税理士や創業支援専門家に相談するのも非常に有効です。
特に初めての方は、自分一人で悩まずに専門家と一緒に進めたほうが、安心して準備できますよ。
②申し込み方法&必要書類のまとめ
相談が終わったら、いよいよ本申し込みです。
日本政策金融公庫の創業融資は、以下の3つの方法で申し込むことができます。
- 窓口で直接提出
- 郵送で提出
- インターネット申込(電子申請)
最近では、電子申請を使えば来店不要で申し込みができるため、忙しい方にも便利です。
申し込みに必要な書類は以下の通りです(事業内容や地域によって追加資料を求められることもあります)。
- 創業計画書(所定の様式)
- 借入申込書
- 通帳のコピー(6ヶ月~1年分)
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 見積書や契約書(設備資金を申請する場合)
- 営業許可証や開業届(必要な業種のみ)
提出書類は不備があると審査がストップしてしまうため、ダブルチェックを忘れずに。
分からないことがあれば、支店や公庫のWebサイトで確認しておくと安心です。
③面談での流れ&よく聞かれる質問内容
書類を提出して数日後、公庫の担当者から面談の案内に関する連絡が入ります。
面談は通常、提出した支店で対面で行われることが多いですが、最近では一部の地域でオンライン面談にも対応しています。
面談の所要時間は約30分~1時間ほど。以下のような内容がよく聞かれます。
- なぜこの事業を始めようと思ったのか
- 事業の強みや差別化ポイントは何か
- 売上や利益の見込みはどうやって計算したのか
- 生活費や借入返済の見通し
- 家族の理解や支援体制はあるか
ポイントは、事前に提出した計画書と矛盾がないこと。
質問の答えに詰まってしまうと、「きちんと考えずに計画したのでは?」と不信感を持たれてしまう可能性もあります。
緊張せず、自分の言葉で丁寧に説明すれば大丈夫。
不安な方は、面談前にシミュレーションをしておくと安心です。
審査結果の通知方法(電話・郵送)とタイミング
面談が終わると、いよいよ結果待ちです。
審査結果は、通常2~3週間以内に電話で連絡が入るのが一般的です。
(※一部地域や混雑期によっては郵送通知となる場合もあります)
融資が決定した場合は、その後すぐに契約手続きに入ります。
逆に、否決(不承認)だった場合も、理由をやんわりと伝えてもらえることが多いので、今後に向けての改善材料として活かすことができます。
関連記事:創業前に必読!日本政策金融公庫の創業融資申し込みの流れと審査対策

審査に落ちないための対策と再挑戦法
日本政策金融公庫の審査は、公的な支援とはいえすべての人が無条件で通るわけではありません。
実際、提出書類や面談内容によっては、残念ながら融資を受けられないケースもあります。
でも、落ちたら終わりではありません!
次に、審査でよくある「つまずきポイント」とその改善策、そして再挑戦に向けたアクションプランをご紹介します。
よくある落ちる原因と改善策
日本政策金融公庫の審査で落ちてしまう主な原因は、大きく以下の5つです。
①自己資金が不足している
💡改善策:コツコツ貯めた履歴が分かる通帳で証明を
見せ金(急な入金や借りたお金)は逆効果。半年〜1年かけて計画的に貯めた実績を示すことが大切です。
②創業計画が現実的でない
💡改善策:具体的な根拠や比較データを計画書に盛り込む
「なんとなく儲かりそう」ではNG。地域の市場規模、競合の価格帯、根拠のある数値を用いて信頼感をアップ。
関連記事:自己資金なしで創業融資を受けられる方法は?5つのポイントと注意点
③信用情報に問題がある
💡改善策:信用情報を事前に確認し、過去の延滞はしっかり説明
携帯電話の滞納やカードローンの遅延履歴は審査に影響します。必要であればCICやJICCで開示請求をして確認を。
④税金や社会保険料の未納がある
💡改善策:滞納分を完納した上で、領収証を提出
未納のままだとマイナス評価になりますが、完納済みであれば再チャレンジの道は開けます。
⑤面談で一貫性がなく、不安を与えてしまった
💡改善策:計画書の内容を自分の言葉で説明できるように練習
「数字は誰かに作ってもらった」という印象を与えるとマイナスに。内容をしっかり理解しておくことが大切です。
このように、審査に落ちる理由には必ず“改善できるヒント”が含まれています。
一度で通らなかったとしても、原因をしっかり分析し、対策を取れば次に繋がります。
再申し込みのポイント
公庫の創業融資は、再申し込みが可能です。
ただし、何も改善せずに再申請しても、結果が変わる可能性は低いため、以下のような点に気をつけましょう。
- 不承認理由をきちんと確認する(担当者にやんわり聞くことも可能)
- 改善策を講じたことを明確に伝える(例:自己資金が倍になった/会計データを整えた等)
- 前回の申請から少なくとも3ヶ月以上の期間をあけて再提出するのが理想
また、再申請の際には、同じ書類を使い回すのではなく、新たに作り直すことが信頼感につながります。
再挑戦は、決してマイナスではなく、「改善できる前向きな姿勢」を見せるチャンスと捉えてOKです。
追加融資・2回目以降の審査について
創業してから半年~1年ほど経つと、追加資金が必要になるケースもあります。
その際に利用できるのが、「追加融資」や「2回目以降の融資」です。
2回目の審査では、以下のような点が重視されます。
- 売上や利益が計画通りに進んでいるか
- 返済がきちんとできているか(遅延なし)
- 会計帳簿が正確に管理されているか
- 前回の資金使途が目的通りに活用されたか
初回とは異なり、実績が判断基準になるため、日々の記帳・会計管理が非常に重要になります。
帳簿がつけられていなかったり、申告が遅れていたりすると、それだけで「この事業は危ないかも」と思われてしまうことも…。
追加融資を見据えている方は、創業直後から帳簿や通帳の管理を丁寧に行っておきましょう。
このように、日本政策金融公庫の審査で落ちてしまったとしても、それはあくまで「現時点での評価」。
しっかり準備し直して再挑戦すれば、次のチャンスで融資が通るケースはたくさんあります。
関連記事:日本政策金融公庫の審査に落ちた場合の再申請のポイントを解説
制度融資・少額融資との違い
創業時に使える融資制度は、日本政策金融公庫だけではありません。
各自治体が実施している「制度融資」や、日本政策金融公庫が提供する「少額融資(小口融資)」など、目的や状況に応じて選択肢があります。
次に、それぞれの融資制度の特徴やメリット・デメリットを比較しながら、どんな方にどの制度が向いているのかをご紹介します。
自治体連携の制度融資とは?メリットや注意点をご紹介
「制度融資」とは、自治体・信用保証協会・金融機関の3者が連携して行う融資制度のことです。
地域によって名称は異なりますが、たとえば「創業支援融資」「中小企業支援資金」などの名前で実施されています。
以下に、制度融資の仕組みやメリット、注意点をまとめてみました。
制度融資の仕組み
- 申し込み先:地元の銀行など民間金融機関
- 保証人:信用保証協会が保証人となる(借主が保証料を支払う)
- 利子補給:一部自治体では利子の一部を負担してくれる制度あり
制度融資のメリット
- 金利が低め(利子補給があると実質0%の場合も)
- 地元自治体とのつながりが生まれる
- 融資金額が比較的高め(数百万円〜1,000万円以上も可能)
制度融資の注意点
- 手続きが煩雑(自治体・保証協会・銀行を通すため時間がかかる)
- 信用保証協会の審査があり、保証料の負担が発生する
- 担保・保証人が求められるケースも
日本公庫の創業融資と比べると、制度融資は利率面で有利な場合がありますが、手続きが複雑なうえ、審査期間が長くなりがちです。
そのため、ある程度時間に余裕がある方や、高額の資金調達を希望する方には向いています。
一方で、「すぐにでも資金が必要!」という方や、「事業経験が浅く、書類整備に自信がない…」という方には、日本政策金融公庫のほうが使いやすいでしょう。
少額融資(300万円以下)と審査のコツ
日本政策金融公庫には、比較的少額の融資を希望する方向けの仕組みもあります。
300万円以下の融資であれば、審査もやや簡易的になり、面談や書類の負担も軽くなる傾向があります。
少額融資の特徴
- 融資希望額が300万円以内の場合、比較的スピーディに審査が進む
- 自己資金の割合が高いと、さらに通りやすい
- 簡潔な創業計画でも対応可能(ただし最低限の根拠は必須)
少額融資の活用シーン
- 自宅開業や小規模スタートアップでの開業資金
- フリーランスやスモールビジネスでの初期運転資金
- 副業から本業へのステップアップ資金
少額融資とはいえ、審査の基本的な視点(計画性・返済能力・信用情報)は変わりません。
特に、通帳の履歴や自己資金の「コツコツ感」は評価されやすいため、準備はしっかりしておきましょう。
このように、同じ「創業融資」といっても、日本政策金融公庫・制度融資・少額融資にはそれぞれ違いがあります。
| 項目 | 日本政策金融公庫 | 制度融資(自治体) | 少額融資(300万円以下) |
|---|---|---|---|
| 金利 | 低め(1.5〜2.5%) | 補助があれば0%も | 同左 |
| 審査期間 | 約2〜3週間 | 約1〜2ヶ月 | 約1〜2週間 |
| 審査難度 | 中(書類+面談) | 高(保証協会も審査) | 低〜中(自己資金多いと有利) |
| 担保・保証人 | 基本不要 | 場合によって必要 | 不要 |
| おすすめ | 初めての創業者 | 高額資金・自治体支援希望者 | 小規模起業・副業独立 |
どの制度を使うべきか迷ったときは、専門家や公的支援窓口に相談してみるのも一つの方法です!
\各種融資についてお悩みの方はご相談ください/
無料相談はこちら!
融資後にやるべきことと注意点
日本政策金融公庫の融資が無事に通ると、ほっと一安心…ですが、本当のスタートはここからです。
資金の使い方、帳簿の管理、将来の追加融資に備えた準備など、実は「融資後の行動」がとても大切です。
ここでは、融資後にやっておきたいことや、ありがちな注意点をまとめてご紹介します。
資金の使い道の管理
まず最も大切なのは、融資で受け取った資金を「計画通り」に使うことです。
日本公庫は、「このお金をどう使うのか?」という前提のもとで審査・承認をしています。
万が一、全く違う使い方をしていたり、使い道が不明瞭になっていたりすると、追加融資の際に信用を失う原因にもなってしまいます。
実践ポイント:
- 資金を入金してもらった口座は、事業専用の口座として管理する
- 設備の購入、仕入れ、広告費など、支出内容を記録しておく
- 領収書や契約書を保存して、資金使途の証拠を残しておく
クラウド会計ソフトやエクセルでも構いませんので、日々の出金・入金をこまめに記録する習慣をつけましょう。
この積み重ねが、将来の追加融資・助成金申請・確定申告などでも役立ちます。
帳簿の整備と確定申告の準備
融資後の事業運営では、お金の出入りをきちんと管理することが信頼の基本になります。
特に創業初年度は、「帳簿ってどうつければいいの?」「確定申告って何をするの?」と不安になる方も多いですよね。
会計知識がなくても、以下のような対策で乗り切れます。
- クラウド会計ソフト(例:freee・マネーフォワード)を活用する
- 税理士と顧問契約を結び、月次でアドバイスをもらう
- 領収書やレシートを月ごとに整理して保管しておく
特に重要なのは、「黒字か赤字か」が把握できる体制を早めに作ることです。
「気づいたら赤字でお金が足りない…」となる前に、数字で経営を見える化することが、次の一手につながります。
また、確定申告では、創業融資の元金返済や利息の扱いなども計上が必要になりますので、早めの準備が肝心です。
返済スケジュールと返済時の注意点
日本公庫の融資には、元金返済の「据置期間(すえおききかん)」が設けられていることが多いです。
たとえば、「半年間は利息だけの支払いでOK」という形ですね。
この期間を有効活用して、売上を安定させたり、顧客を増やしたりするのが理想ですが、据置期間が終わると、毎月の元金返済が始まります。
注意点として、以下の点が挙げられます。
- 据置期間終了後は、支払いが一気に増えることを忘れずに!
- 「元金+利息」の返済額を月次計画にきちんと組み込む
- 口座残高の管理をこまめに行い、引き落とし不能にならないよう注意
もしも資金繰りが厳しくなってしまった場合は、放置せず、早めに公庫の担当者に相談することが大切です。
条件変更(返済期間の延長や一時的な利息のみ支払いなど)も可能な場合があります。
次の資金調達に備える行動とは?
創業融資は、あくまで「スタート資金」。
事業が成長していく過程で、「新たに機械を入れたい」「人を雇いたい」「新店舗を出したい」など、再び資金が必要になることもあるでしょう。
そのときに備えて、次のような行動を心がけておくとスムーズです。
- 定期的に損益計算書・資金繰り表を作成する
- 月次で数字を見て、経営状況を把握する習慣をつける
- 黒字決算を目指して経費バランスを調整する
- 信用情報や税金の納付状況を良好に保つ
そして何より、「公庫と良好な関係を築いておくこと」が大きな財産になります。
些細なことでも相談に乗ってもらえるよう、困ったときにはこまめに連絡を取る姿勢が、次回の融資や補助金活用の際にプラスに働くこともありますよ。
まとめ
ここまで、日本政策金融公庫の創業融資について、審査のしくみから申し込みの流れ、審査に落ちないための対策、そして融資後にやるべきことまで、幅広くご紹介してきました。
創業融資は、単に「お金を借りる手段」ではありません。
あなたがこれから始める事業に対して、社会的な信頼を得るための大切な一歩です。
だからこそ、不安なまま申請するのではなく、「きちんと準備して、納得のいく形で審査に臨むこと」が成功の秘訣になります。
***
創業計画書の作成、自己資金の整理、面談対策…やることが多くて「何から手をつければいいかわからない」とお困りではありませんか?
そんな方は、創業支援の専門家に相談してみることをおすすめします。
第三者の視点が入るだけで、計画の甘さに気づけたり、強みを再確認できたりと、大きな安心につながります。
当サイト(熊本創業融資相談室)では、創業前の方・初めて融資を検討している方を対象に、無料相談を実施中です。
- 公庫に提出する創業計画書の作成サポート
- 自己資金のチェックとアドバイス
- 面談で聞かれるポイントの事前シミュレーション
- 制度融資や補助金の併用についてもご提案可能
など、あなたに合わせたサポートを行っています。
\無料相談はこちらから/
一人で悩む前に、どうぞお気軽にご相談くださいませ☺
\お気軽にお問合せください☻/