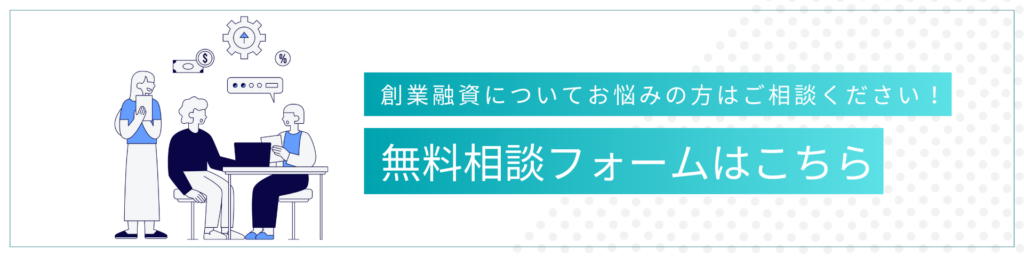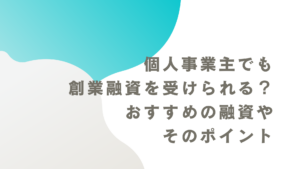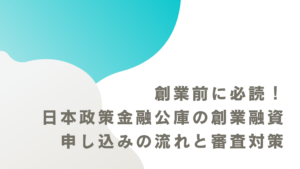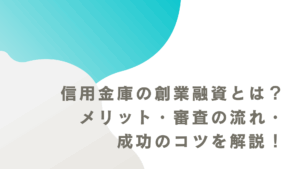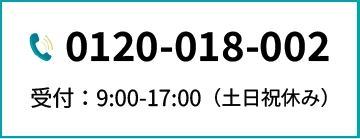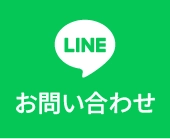日本政策金融公庫の審査に落ちた場合の再申請のポイントを解説
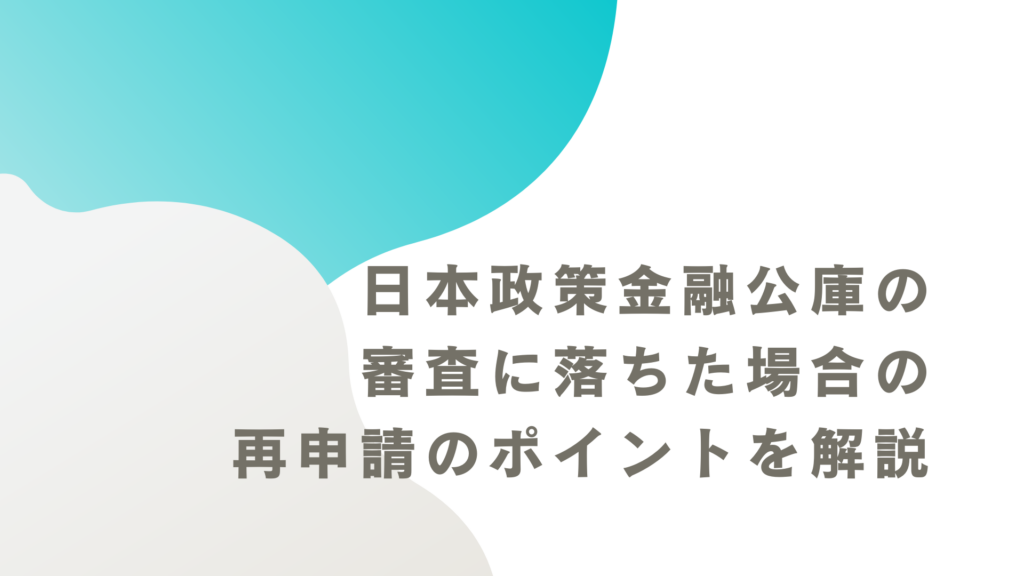
日本政策金融公庫は、一回審査に落ちてしまった場合、原則6ヶ月の期間を空けて申請をしなければなりません。しかし、これは原則であって、例外も多いのをご存知でしょうか?
実は、社長の説明不足が原因で落とされてしまうことが少なくありません。
多くの場合、社長は日本政策金融公庫の担当者に、事業モデルについて熱く語られます。しかし、日本政策金融公庫の担当者は経営者の経験がありません。事業モデルを聞いて融資の判断をすることは非常に難しいのです。
ただ実は、もっとわかりやすい判断基準があります。その判断基準に沿って説明し直し、可能性を感じてもらうことができれば、融資の再申請も可能です。
今回は、日本政策金融公庫の審査を落ちる他の理由や審査通過のためのポイント、落ちてしまった際の対処法などをご紹介いたします!
\融資についてお悩みの方はご相談ください/
無料相談はこちら!
日本政策金融公庫の審査に落ちる主な理由
「せっかく書類も準備して、面談にも行ったのに落ちてしまった…」
日本政策金融公庫の融資審査に落ちると、がっかりしてしまいますよね。でも、落ちてしまったのには、必ず何らかの理由があります。
そこで、よくある落ちる理由を解説していきます。
信用情報に問題がある
審査で最もチェックされるのが「信用情報」です。過去にローンやカードの延滞があったり、自己破産の履歴があると、融資の審査には大きく影響します。
金融機関から日頃から指導や改善を促されているにも関わらず、改善の意志がない経営者(会計を適時に提示しない、依頼された資料を期限までに提出しない、約束をしていたにも関わらずドタキャンなど)や、金融機関に対して嘘をついていたりしていてもアウトです。
「数年前のことだから大丈夫だろう」と思っていても、情報は信用情報機関にしっかりと記録されています。まずは、ご自身の信用情報を確認してみることが大切です。
自己資金が不足している
「自己資金ゼロだけど、やる気はある!」という気持ちは素晴らしいですが、公庫の審査では自己資金の有無がかなり重要視されます。
目安として、創業に必要な資金の3割程度の自己資金があると評価が高くなります。貯金や積立など、日ごろからしっかり準備しておくことがポイントです。
融資希望額が大きすぎる
起業にはお金がかかりますが、「まずは多めに借りておこう」という考えで高額の融資を申し込むと、審査でマイナス評価を受けることも。
事業の規模や売上見込みに対して、「その金額は本当に妥当か?」と審査員は見ています。必要以上の借入は、むしろ審査に不利になることがあるので、慎重に金額設定をしましょう。
資金使途が不明確
「とりあえず運転資金がほしいです」とざっくりした説明では、公庫の審査には通りません。
どんな目的で、どんな支出に充てるのか、資金の使い道(資金使途)を具体的に説明できるかが大切です。たとえば、「店舗内装費に○○万円」「仕入れ資金に○○万円」など、できるだけ細かく記載しましょう。
事業計画書の内容が不十分
事業計画書は、いわばあなたの「ビジネスの設計図」です。
この内容があいまいだったり、数字の根拠が乏しかったりすると、「この人、本当に事業が続けられるのかな?」と疑問を持たれてしまいます。
市場調査の内容や、売上・利益の見込み、今後の戦略まで、しっかりと説得力のある事業計画書を作ることが大切です。
直近の決算書の内容に問題がある
日本政策金融公庫で融資を受ける場合は、決算書などの書類の提出が必要です。
まず、法人として融資を申請する場合に必要な決算書類は以下の通りです。
これらはあなたの企業の経営状況を示す重要な資料ですので、正確に準備することが大切です。
- 決算申告書(2期分):事業を始めてから2期経過していない場合は、申告済みのものを提出しましょう。
- 試算表:決算期から半年以上経過している場合には、この試算表も必要になります。
次に、個人事業主として融資を受ける場合は以下の書類が必要です。
- 申告済確定申告書(2年分):開業前は不要ですが、開業後2期経過していない場合には、申告済みのものを提出してください。
直近の売上が上がっていないケースや、過去から採算が全く取れておらず、継続的に事業として成り立っていないケース(創業して1年内は除く)返済能力がないと判断され、融資を受けられないことが多いです。
経験が不足している
まったく未経験の分野での起業だと、どうしても審査では厳しい目で見られます。
たとえば飲食業での起業なのに、調理や経営の経験がまったくないと「ちゃんとやっていけるのか?」と不安視されがち。
これまでの職務経験や、研修・勉強したことなどを、しっかりアピールしましょう。
面談での対応に失敗した
面談では、書類に書かれていないこともたくさん質問されます。
緊張してうまく答えられなかったり、説明があいまいになったりすると、「この人にお金を貸しても大丈夫かな?」という不安を与えてしまいます。
落ち着いて話せるように、事前に想定質問の練習をしておくのがおすすめです。
必要な許認可を取得していない
業種によっては、営業に必要な「許可」や「認可」を事前に取得しておく必要があります。たとえば飲食店なら保健所の許可、美容室なら美容所登録など。
これが取得できていないと、「そもそも事業が始められないのでは?」と判断されてしまうことも。
審査前に、必要な許認可をしっかり確認しておくことが大切です。
日本政策金融公庫の審査に通るためのポイント
「一度落ちたけど、今度こそは通したい!」
「初めての融資申請、絶対に失敗したくない!」
そんな方のために、日本政策金融公庫の審査に通るための“コツ”を3つの視点からご紹介します。しっかり準備すれば、審査通過の可能性はグッと上がりますよ。
自己資金と資金使途を明確に
まずはここが基本中の基本!
自己資金は「自分でどれだけ準備したか」という、いわば起業への本気度をはかる大きな指標です。
最低でも創業に必要な資金の3割程度は用意しておきたいところです。
さらに、「お金を何に使うのか?」という資金使途の明確化も重要なポイント。たとえば、
- 店舗の内装費に100万円
- 開業時の仕入れに50万円
- 広告宣伝費に30万円
…というように、具体的な金額と使い道を明記しておくと、審査官に安心感を与えられます。
説得力のある事業計画書を作る
事業計画書は、あなたの想いと未来をカタチにする“最重要書類”です。
売上や利益の見込みを数字で示すだけでなく、以下のような要素も丁寧に記載すると、説得力がぐっと増します。
- なぜこの事業を始めたいのか(創業動機)
- 自社の強みや差別化ポイント
- 市場調査の結果や競合分析
- お金の流れ(売上、経費、利益の予測)
- 1年後、3年後の目標
数字の根拠があいまいだったり、抽象的すぎる内容だと、審査官は不安になります。
逆に、「ここまで考えているのか!」と思わせる内容だと、審査官の評価は一気にアップしますよ。
面談対策を万全にする
書類がしっかりしていても、面談の対応が悪ければ審査落ちする可能性も…。
面談では、書類の内容に沿って質問されたり、「この人は本当に実行できるのか?」という人間性もチェックされます。
よくある質問としては、
- なぜこの事業を選んだのか?
- 売上が伸びなかった場合の対策は?
- 借入金の返済はどう考えているか?
などが挙げられます。
これらの質問に対して、自分の言葉で、しっかりと自信を持って答えられるよう準備しておきましょう。模擬面談をしてみるのも効果的です。
準備と対策を怠らなければ、日本政策金融公庫の審査通過は決して夢ではありません。
日本政策金融公庫の審査に落ちてしまった場合の対処法
「まさか落ちるとは…」
「何がいけなかったのか…」
そんなふうに落ち込んでしまう方も多いですが、実は審査に落ちた後の行動がとても大切なんです!
落ちたからといって夢をあきらめる必要はありません。ここでしっかりと対処すれば、次の再チャレンジで融資を勝ち取ることは十分可能ですよ。
原因分析と改善
まずは「なぜ審査に落ちたのか?」その原因を冷静に振り返りましょう。
融資申込者に対して、結果通知に明確な「理由」は書かれていないことが多いですが、以下のような点を見直すことで原因のヒントが見つかることがあります。
- 自己資金が少なかった
- 売上予測が楽観的すぎた
- 面談での受け答えが曖昧だった
- 許認可が未取得だった
- 経験や実績が不足していた
できれば、自分だけで悩まずに専門家に事業計画書を見てもらうと、客観的なアドバイスがもらえますよ。
再申込までの準備期間の活かし方
再度申し込む場合、すぐに再申請してもあまり良い結果にはなりません。
少なくとも3〜6ヶ月程度は空けるのが一般的です。
この期間は「準備期間」だと考えて、
- 事業計画書をブラッシュアップ
- 面談対策を見直す
- 資金計画の現実性を高める
- 市場調査を深める
といった取り組みに活用しましょう。
この数ヶ月の努力が、次回の審査の印象を大きく変えます!
自己資本を高める工夫
日本政策金融公庫の審査では、自己資金がどれだけあるかが重要なポイントになります。
「自己資金が足りなかったかも…」という方は、次のような方法で資金を増やす工夫をしてみましょう。
- 副業やアルバイトで貯金を増やす
- 不要な出費を減らして節約
- 家族や知人からの支援(贈与ではなく、返済前提の借入ならOKな場合も)
自己資金の増加は、単に「お金がある」だけでなく、「事業への本気度」や「計画性」を評価される材料にもなります。
専門家への相談
再チャレンジを考えている方には、税理士や中小企業診断士などの専門家に相談するのがおすすめです。
プロの視点からアドバイスをもらうことで、見落としていた課題に気づけることもあります。
特に、事業計画書の改善や、自己資金の考え方、面談の準備など、融資申請のトータルサポートをしてくれる専門家もいます。
\融資についてお悩みの方はご相談ください/
無料相談はこちら!
他の融資制度の検討
日本政策金融公庫だけが選択肢ではありません!
審査に落ちてしまった場合でも、次のような他の融資制度を検討するのも一つの方法です。
- 信用保証協会付きの制度融資(地方自治体が用意しているケースあり)
- 商工会議所や商工会の創業支援制度
- 地域金融機関の創業支援ローン
- 無利子・無担保の特別支援制度(期間限定のケースも)
自分の状況や事業計画に合った制度が見つかれば、そちらから再チャレンジするのも検討してみましょう。
融資の再申請の際の6つの説明パターン
融資の再申請を行う際には、大きく下記の6つのパターンがあります。
審査のポイントに沿った上で、
- 社長が同じ担当者に、再度説明を行う
- 社長が違う担当者に、再度説明を行う
- 社長が違う支店の担当者に、説明を行う
- 税理士等の専門家を窓口に、同じ担当者に説明を行う
- 税理士等の専門家を窓口に、違う担当者に説明を行う
- 税理士等の専門家を窓口に、違う支店の担当者に説明を行う
一般的に、”6.税理士等の専門家を窓口に、違う支店の担当者に説明を行う”に進むほど、再度申請できる可能性は高くなります。
一度落ちてしまっても再申請の可能性はありますが、なるべく一度の申込で通るよう準備することをお勧めします。
日本政策金融公庫の担当者は一度落とした案件については、なかなか取り合ってくれませんが、専門家が対応することによって、取り合ってもらえる可能性が高まります。
当創業融資相談室では、お客様自ら申請をして審査に落ちてしまった方からサポートをご依頼をいただくことも多くあります。
当社にてサポート後、再申請を行ったケースでは、高い確率で融資を獲得することができています。
ただし、当社がお客様からのご依頼を受託した場合のみ、融資獲得となっており(つまりは審査落ちの原因があり、その原因を改善することが可能であると判断した場合のみ受託しているため)、ハードルは高いことはご了承くださいませ。
創業融資に関するよくある質問(FAQ)
創業融資を検討している方からは、よく似た疑問や不安の声が寄せられます。
ここでは、特によくある質問をまとめて解説しますので、あなたの不安解消に役立ててくださいね!
Q1.個人と法人、審査に有利なのは?
「個人事業主よりも法人の方が有利なんですか?」という質問、よく聞きます。
実際のところ、審査の有利不利は“形式”よりも“中身”次第です!
法人だからOK、個人だからNGということはありません。
重要なのは事業計画の信頼性や自己資金の準備状況、代表者の経験や信用情報です。
ただし、法人は社会的な信用がやや高く見られる傾向はありますし、将来の成長計画や従業員雇用などがあると、プラス評価になりやすいです。
Q2.担保や保証人は必要?
日本政策金融公庫の「新創業融資制度」などでは、原則として担保・保証人は不要です!
これは、創業者にとってとても心強い制度ですよね。ただし、「法人代表者の連帯保証」は求められることが多いので、まったく無保証とは限らない点には注意が必要です。
また、制度によっては担保が必要なケースもあるので、しっかり確認しておきましょう。
Q3.審査結果はいつわかる?
気になる審査結果、平均的には申込から2〜3週間ほどで通知されることが多いです。
ただし、書類の不備があった場合や、面談日が遅れた場合 などは時間がかかることも。
特に繁忙期(年度末・年度初めなど)は時間がかかる傾向があります。スケジュールには余裕をもって申し込みましょう。
Q4.再チャレンジはできる?
はい、再チャレンジは可能です!
ただし、前回と同じ内容で再申請しても、結果は変わりません。
再チャレンジするなら、以下のような改善と準備がカギです。
- 自己資金を増やす
- 事業計画書の内容を見直す
- 市場調査や根拠の明確化
- 面談対策を徹底
しっかり準備して再チャレンジすれば、再申請で融資が通ったというケースも多数あります!一度の失敗で諦めず、前向きに進みましょう。
一度審査に落ちてもあきらめないで!
融資を受けることができるかどうかの”目安となる基準”は存在しています。
「二度目だから無理かも…」と考えるのは早計です。
まずは専門家に相談をしてみることをお勧めします。
熊本創業融資相談室では、日本政策金融公庫の融資を受けるためのサポートや、今後の事業を改善していくためのサポートを行っています。
まずはあなたの事業の現状についてお聞かせください。
もちろん無料でご相談を受け付けておりますので、お気軽にお問合せくださいませ。
無料相談のご予約は、以下の申し込みリンクまたはお電話でお申し込みいただけます。
皆様からのご相談を心よりお待ちしております。
\お気軽にお問合せください☻/