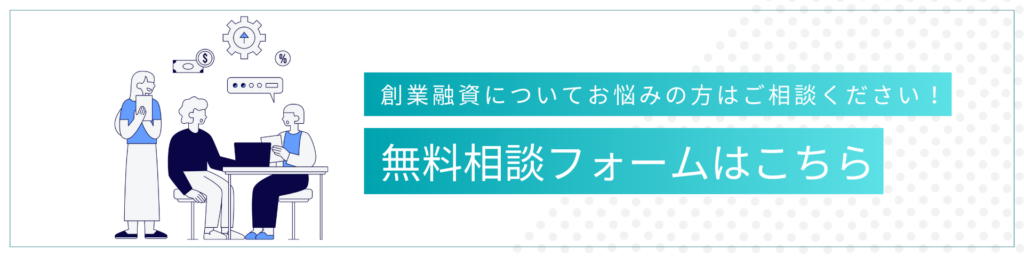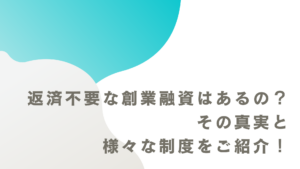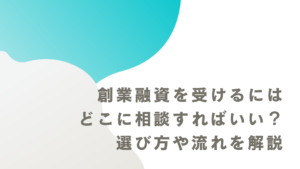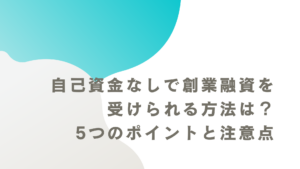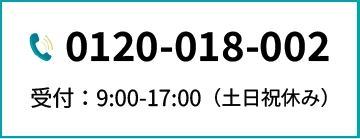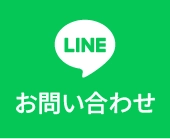創業融資制度の据置期間とは?メリット・デメリットや活用方法を解説!
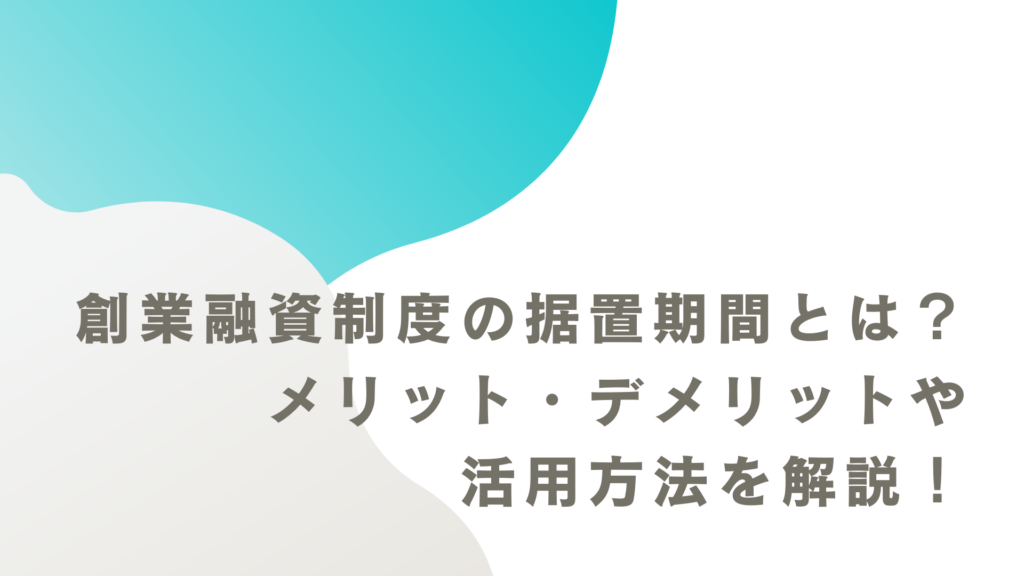
「創業融資には“据置期間”があるって聞いたけど、そもそも何のこと?」
「資金繰りを楽にする制度って本当?」
そんな疑問をお持ちの方へ向けて、この記事では創業融資の「据置期間」について、メリットや注意点を解説していきます。
実は、この期間をうまく活用できるかどうかが、創業初期の資金繰りや事業の立ち上がりに大きな影響を与えるんです。
創業を考えている方や、融資を検討している方にとって、役立つ内容になっていますので、ぜひ最後まで読んでみてください!
\ 創業融資についてお悩みの方はご相談ください /
無料相談はこちら!
創業融資の「据置期間」とは?
創業融資の説明を受けたら、「据置期間がありますよ」って言われたことがある方がいらっしゃいませんか?
創業したばかりのタイミングは、売上がまだ安定していなかったり、設備投資や広告費などでお金が出ていきがちです。
そんなときに、「今すぐ返済が始まるのはちょっとキツイな…」と感じる方も多いです。
そこで登場するのが、「据置期間」という仕組み。
これは、創業融資を受けたあと、一定期間“元金の返済を待ってもらえる”制度のことです。
据置期間の基本的な仕組み
据置期間とは、ズバリ、融資を受けてから一定期間、元本の返済が免除される期間のこと。
たとえば、創業融資で1,000万円を借りたとしても、この期間中は元金を返さなくてOK。
※ただし、多くの場合、利息だけは支払う必要があります。
措置期間の長さはケースバイケースですが、6ヶ月〜1年程度が一般的です。
一部の制度では、2年の措置期間が設けられることもあります。
つまり、この期間は「返済スタートの助走期間」とも言えるわけですね。
据置期間が設けられる理由
ではなぜ、このような据置期間があるのでしょうか?
答えはシンプルで、創業初期の資金繰りを楽にしてもらうためです。
創業当初は、
- お客様がまだ少ない
- 販売ルートが整っていない
- 設備や備品の購入にお金がかかる
- 人件費や家賃などの固定費もかかる
など、売上よりも出費が先にくるのが普通です。
そんなときに、いきなり毎月10万円、20万円と返済が始まってしまうと、キャッシュがショートするリスクが出てきます。
融資制度としても、返済できなくなるより、しっかり準備してから返済をスタートしてほしいという思いがあるんですね。
日本政策金融公庫の据置期間
創業融資といえば、多くの方が利用を検討するのが日本政策金融公庫です。
この日本政策金融公庫でも、創業者の資金繰りを応援するために、据置期間を取り入れています。
公庫の創業融資で設定される据置期間はどれくらい?
日本政策金融公庫では、創業融資を利用する際に申請時に希望する据置期間を設定することができます。
公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」では、設備資金と運転資金の据置期間は5年以内と設定されています。
もちろん据置期間が長くなる分、利息の支払期間が延びたり、返済期間が圧縮されることで毎月の返済額が増えることもあるので、バランスを見ながら設定することが大切です。
据置期間は自動でつくの?申請が必要?
これはよくある疑問ですが、据置期間は自動的に設定されるわけではありません。
融資申込時の事業計画書などに、希望する据置期間を記載し、公庫担当者との面談でしっかりとその理由を説明する必要があります。
例えば、
- 「初期投資が大きいため、すぐに返済が難しい」
- 「サービスリリースまで数ヶ月かかるため、その間の資金繰りを安定させたい」
といった事情があれば、きちんと伝えることで、据置期間が認められやすくなります。
創業期は何かと不安が多い時期。
そんな中で、据置期間があることで「まずは売上を安定させてから返済を始められる」という安心感がありますよね。
日本政策金融公庫の創業融資は、返済期間や金利面も含めて創業者に優しい設計になっているのが大きな特徴です。
据置期間のメリット・デメリット
さて、ここまで「据置期間」がどんな仕組みなのか、日本政策金融公庫での対応も含めてご紹介してきました。
では実際に、措置期間を設定するとどんなメリットがあって、どんな点に注意すべきなのか?
ここでは、創業時に融資を受ける立場として知っておきたいポイントをわかりやすく解説していきます!
創業初期の“資金繰りをラクにする”大きなメリット
据置期間の最大のメリットは、なんといっても「返済がすぐに始まらない」ことによる資金的な余裕です。
創業間もない時期は、売上がまだ安定しないことが多いため、いきなり元金の返済が始まると、キャッシュフローがカツカツになる可能性も。
据置期間があれば、その期間は利息だけの支払いでOKなので、売上が立ち始めてから返済をスタートできるという精神的な安心感も大きくなります。
また、資金に少し余裕があることで、必要な設備投資を我慢したり、焦らずに事業に専念できるため、事業の成長準備にしっかり時間をかけられるのも嬉しいポイントです。
デメリットも理解しておこう!据置期間の注意点
一方で、「据置期間があるから安心!」とばかりに楽観視するのはNGです。
据置期間には、いくつか注意しておくべきデメリットもあります。
①利息の支払期間が長くなる
措置期間中でも、ほとんどの場合で利息の支払いは必要になります。
つまり、元本を返していない間にも、毎月の利息はかかり続けるということ。
たとえば1年間の措置期間があれば、その間の利息だけで数万円〜数十万円になる可能性もあります。
元金が減らない=利息が一定額でかかり続けるという点には注意が必要です。
②据置期間後の返済額が大きくなることも
据置期間を長くすると、そのぶん返済期間が短くなるケースもあります。
つまり、据置期間が終わったあとに月々の返済額がドンと重たくなる可能性も。
「据置期間が終わってからが大変だった…」という声も実際にありますので、返済開始後のシミュレーションをきちんとしておくことが大切です。
メリット・デメリットを比較して、自分に合った選択を
据置期間は、うまく使えば創業期の資金繰りをかなりラクにしてくれる強い味方です。
でも、何も考えずに設定してしまうと、後で返済が重たくなって苦労することもあります。
大切なのは、
- どのくらいの売上がいつから見込めそうか
- 自分の事業にとって、いつから返済可能か
- 毎月いくらまでなら返済できるか
こうした現実的な視点で考えることです。
不安な場合は、税理士や融資に詳しい専門家に相談するのもオススメです。
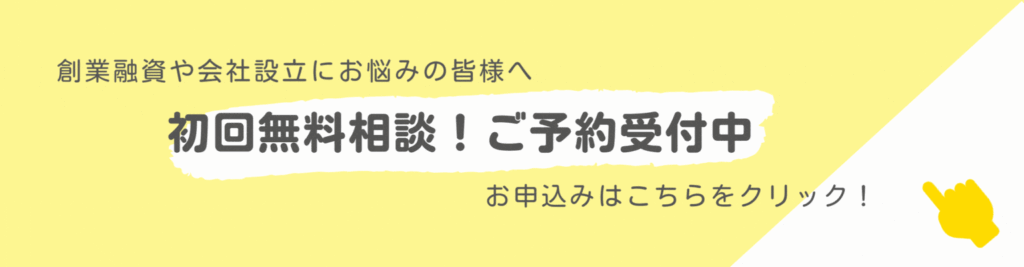
据置期間をうまく活用するポイント
「創業融資の措置期間って便利そうだけど、どう使えばいいの?」
そんな声も多く聞かれます。
実はこの据置期間は、うまく活用するかどうかで、創業期の経営の安定感が大きく変わってきます。
ここでは、措置期間を最大限に活かすためのポイントを3つの視点から解説していきます!
1. 売上が安定するまでの“資金クッション”として使おう
まず大事なのは、「据置期間は、あくまで“準備期間”」という意識を持つこと。
売上がまだ安定しない創業期においては、仕入れや広告費、家賃、スタッフの給与など、
お金が出ていくスピードの方が圧倒的に早いのが現実です。
そこで据置期間をうまく使えば…
- 利息だけの支払いに抑えられるので資金繰りがラク
- 売上アップのための施策(PR、広告、販促)に集中できる
- 顧客づくりや商品開発に余裕を持って取り組める
つまり、「事業を軌道に乗せるまでの大事な猶予期間」として有効に活用できます。
2. 据置期間終了後の返済に備えた“逆算プラン”を立てよう
次に重要なのが、「据置期間が終わったらどうなるのか?」という未来を見据えた準備です。
返済がスタートすると、当然ながら毎月の支出が増えます。
たとえば、月5万円の返済が始まると、1年間で60万円が出ていく計算に。
そこで大切なのが、「据置期間が終わるまでに売上がどのくらい必要か?」を逆算しておくことです。
- 月いくら売り上げれば返済も事業も回るか?
- 固定費をどれだけ抑えておくか?
- 資金繰り表をきちんと作っておくか?
など、事前に計画しておくことで“融資後の落とし穴”を回避できます。
3. 専門家と相談して「無理のない期間設定」を!
据置期間は便利な部分があるとはいえ、長く取りすぎると後の返済がきつくなったり、短すぎると資金が回らない等と、バランスが難しい部分もあります。
そんな時におすすめなのが、税理士や融資に詳しい専門家との相談です。
- どのくらいの期間を取るのが理想か?
- 毎月の資金繰りの見通しはどうか?
- 据置期間が終わった後のリスクは?
など、第三者の視点から冷静にアドバイスをもらえることで、より安全に創業融資を活用できます。
特に「創業時の資金繰りに不安がある」「事業計画がはじめてで不安…」という方は、
専門家の力を借りることで、グッと安心してスタートを切ることができるでしょう。
創業融資で据置期間が設けられないケースとは?
そんな据置期間ですが、必ずしも全員が利用できるわけではありません。
「当然つけてもらえると思ってたのに、措置期間がゼロだった…」という声も実際にあります。
では、どんなときに措置期間が設けられないのでしょうか?
ここでは、よくある3つのケースをご紹介します。
ケース1:事業計画に“余裕”がないと判断された場合
日本政策金融公庫などの金融機関は、融資を行う際に「事業計画の妥当性」をしっかり確認します。
その中で、売上の利益の見通しが甘かったり、返済能力が不明といった点があると、「返済を先延ばしにするリスクがある」と判断される場合があります。
その結果、「据置期間は設けずに早めに返済を始めてもらおう」という判断がされることもあるのです。
ケース2:すでに事業を開始していて売上が立っている
「創業融資」とは言っても、すでに事業をスタートしてから申し込む方も多いですよね。
ただし、事業開始後ある程度の売上があると、「もう返済能力がある」と見なされて、据置期間が不要と判断されるケースがあります。
たとえば、開業から半年以上経っていたり、月の売上が安定している場合は、「すぐに返済を始めても問題ない」と判断されやすくなるのです。
ケース3:融資希望者の信用状況に懸念がある
創業融資は無担保・無保証で借りられる制度ですが、
そのぶん、申込者の「信用力」がとても重要な判断材料になります。
たとえば、過去にローンやクレジットの延滞があったり、他に多額の借入があるなど、金融機関が「リスクがある」と感じた場合には、据置期間をつけずに早めに返済開始してもらおうと判断されることがあります。
まとめ
創業融資の「据置期間」は、創業者にとって非常にありがたい制度です。
返済開始を少し遅らせることで、立ち上げ期の資金繰りに余裕を持たせることができ、事業に集中することが可能になります。
ただし、その反面、
- 措置期間が永遠に続くわけではない
- 設けられないケースもある
- 終了後の返済に備えた計画が必要
といった点を理解しておくことも大切です。
うまく活用するためには、しっかりとした事業計画と、将来を見据えた資金繰りの見通しが欠かせません。
もし、創業融資や据置期間の活用について不安がある場合は、創業支援や融資のサポート実績が豊富な税理士に相談するのがベストです。
特に、熊本で創業をお考えの方には、当熊本創業融資相談室にご相談いただければ、創業支援はもちろんのこと、会社設立後も税務や会計面からもサポートすることが可能です!
あなたの事業スタートを、スムーズに、そして安心して進めていきましょう!
\ お気軽にお問合せください☻ /