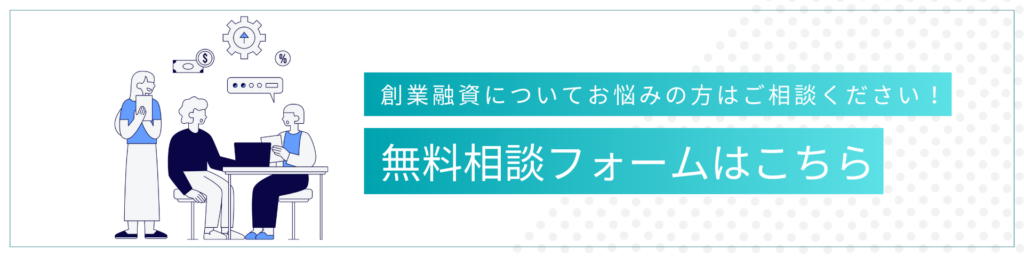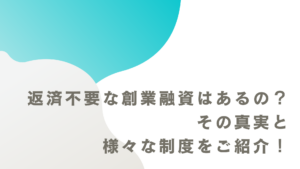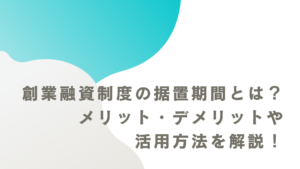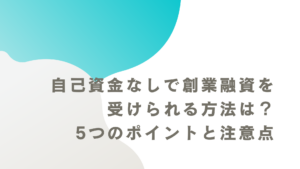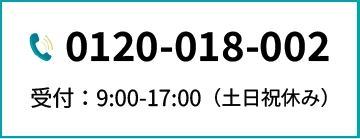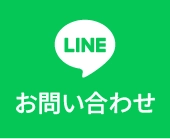創業融資を受けるにはどこに相談すればいい?選び方や流れを解説
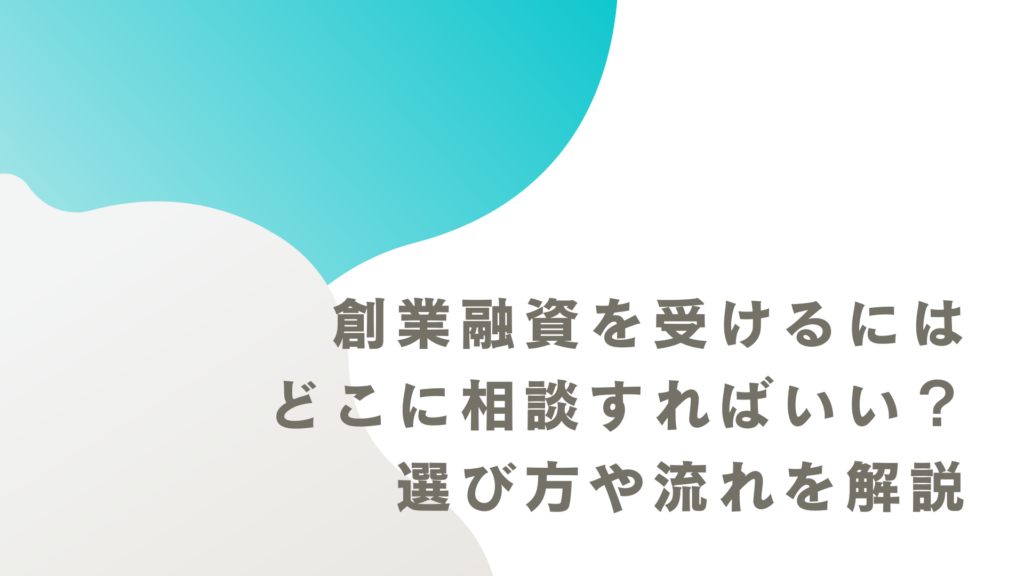
「創業融資を受けたいけれど、一人で申請するのは不安…」
そう思っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか?
この記事では、創業融資の基礎から、どこに相談すればいいのかなどをわかりやすく解説します。
この記事を通して、創業融資を受けることを検討中の方のお力となりましたら幸いです。
\創業融資についてお悩みの方はご相談ください/
無料相談はこちら!
創業融資とは何か?
「いつか自分のお店を持ちたい」「独立してビジネスを始めたい」そんな夢を叶えるために、何より必要になるのが“お金”です。でも、創業前や創業して間もないタイミングでは、売上も実績も少なく、資金調達に苦労する方が多いのが現実…。
そんなときに頼りになるのが「創業融資」です。
創業融資とは、その名のとおり、起業する人や創業して間もない人を対象にした融資制度のことです。主に国や自治体、金融機関が提供していて、「これから頑張りたい!」という方を応援する仕組みです。
事業計画書を提出したり、自己資金の有無をチェックされたりしますが、きちんと準備すれば、実績がなくても融資を受けられる可能性があるのが大きなポイント。
つまり、「これから頑張りたいけどお金が足りない…」という方の背中を押してくれる、心強い制度なんですね。
では、創業融資にはどんな種類があるのでしょうか?次で詳しく見ていきましょう!
創業融資にはどんな種類がある?
創業融資にはいくつか種類があります。それぞれ特徴があるので、自分の状況に合ったものを選ぶのがポイントです。
1. 日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」
創業融資といえばまず名前が挙がるのが、日本政策金融公庫(にっぽんせいさくきんゆうこうこ)が行っている「新規開業・スタートアップ支援資金」です。
この制度の大きな魅力は、担保や保証人が不要で利用できるという点。創業前後の実績が少ない段階でも、しっかりした事業計画があれば、融資が通る可能性があるんです。
また、融資までのスピードも比較的早く、平均で1ヶ月〜1ヶ月半ほど。審査はありますが、「これから創業する方」にとっては、非常に心強い制度といえます。
2. 自治体の制度融資
地方自治体でも、創業支援の一環として独自の融資制度を設けているところがあります。これを「制度融資」と呼びます。
特徴は、自治体と金融機関、そして信用保証協会が連携している点。たとえば、自治体が金利の一部を負担してくれることがあったり、信用保証協会が保証してくれることで、金融機関も融資をしやすくなります。
自治体によって内容は異なるので、まずは自分が住んでいる、あるいは事業を始める地域の制度を調べてみるのがオススメです。
3. 民間の金融機関による創業融資
民間の銀行や信用金庫などでも、創業者向けの融資商品を取り扱っている場合があります。
ただし、こちらは少しハードルが高め。なぜなら、民間の金融機関は「返済能力」をより重視する傾向があるからです。事業の見通しが甘かったり、自己資金が少なかったりすると、審査が通りづらいことも…。
でも、信用金庫など地元密着型の金融機関は、意外と創業支援に積極的なこともあるので、一度相談してみるのもアリです。
創業融資のメリットとデメリット
「創業融資っていいことばかりなの?」と思われるかもしれませんが、もちろんメリットもあればデメリットもあります。ここでは、創業融資の“良い点”と“注意したい点”を両方見ていきましょう。
創業融資のメリット
1. 実績がなくても資金調達できる
創業直後って、売上や利益の実績がないのが普通。でも、創業融資は「これから頑張る人」を対象としているので、実績がなくても事業計画がしっかりしていれば融資が通る可能性があります。
2. 金利が比較的低め
特に日本政策金融公庫や自治体の制度融資は、金利が比較的低めに設定されていることが多く、負担が軽くて済みます。
3. 自己資金だけでは届かないことが実現できる
「あと500万円あれば理想のお店ができるのに…」そんなときに、融資があると夢にグッと近づきます。開業資金が増えれば、内装や設備にもこだわれて、スタートからしっかりしたお店づくりができます。
創業融資のデメリット
1. 審査がある
当然ですが、誰でも無条件でお金が借りられるわけではありません。事業計画の内容や自己資金、経験、返済の見込みなどをもとに、しっかりと審査されます。
2. 返済のプレッシャーがある
融資を受けたら、当然ながら返済が必要です。売上がなかなか伸びないときや、赤字になってしまったときでも、返済は続けなければなりません。「赤字決算 融資」は可能性がゼロではないですが、難易度はグッと上がるため、できるだけ黒字経営を目指すことが大切です。
3. 時間と手間がかかる
融資を申し込むためには、書類の準備や打ち合わせ、面談などが必要です。慣れていないと、書類をそろえるだけでも大変…。そのため、専門家のサポートを受ける方も多いです。
創業融資を申し込むために必要な準備
融資の審査では、「この人にお金を貸して大丈夫か?」が見られます。つまり、「計画性があるか」「返済できそうか」がカギになるんです。
その判断材料として必要なのが、事業計画書です。これが“融資の合否を左右する”と言っても過言ではありません!
事業計画書の重要性
事業計画書とは、「どんなビジネスを始めるのか」「どうやって売上を上げていくのか」「将来的にどんな成長を見込んでいるのか」などを、数字とともにわかりやすくまとめた資料のこと。
たとえばカフェを開業したい場合、「立地はどこなのか」「ターゲットはどんな人たちか」「1日に何人のお客様が来て、いくらの売上を見込んでいるのか」などを明確にします。
計画書がしっかりしていれば、審査担当者に「この人なら大丈夫そうだな」と安心感を与えられるんですね。
逆に、ざっくりしすぎた内容だったり、根拠のない数字ばかり並べた計画書だと、「この人、本当に大丈夫かな…?」と思われてしまうことも。
とはいえ、完璧な書類を最初から作る必要はありません!一歩ずつ、自分の考えを整理しながら作っていけば大丈夫です。必要に応じて、専門家に相談するのもおすすめです。
必要書類と準備するもの
創業融資を申し込む際には、事業計画書の他にもいくつかの書類が必要になります。これが意外と多いので、早めにチェックしておくと安心です。
代表的な必要書類は以下の通りです。
- 事業計画書
- 創業に関する具体的な資料(店舗の図面、見積書、契約書など)
- 本人確認書類(免許証など)
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 自己資金の確認資料(通帳のコピーなど)
- 確定申告書や源泉徴収票(前職がある場合)
特に大事なものが、自己資金の証明です。口頭で「300万円自己資金があります」と言っても、通帳で実際に積み立てた記録がなければ信用されません。
「開業費用の見積書」や「店舗の賃貸契約書」なども、事業の具体性を示すためには大切な資料になります。
ここでつまずく方が多いので、計画段階から少しずつ書類を集めておくのがポイント。突然「あれが足りない!」「間に合わない!」と焦らなくて済みます。
創業融資の面談にあたる注意点と準備
例えば日本政策金融公庫の創業融資では、「面談」がとても重要です。
つまり、ここが実質的な“審査”の入り口になります。
公庫の面談は怖いものではありません。担当者は基本的に親切ですし、こちらの話をちゃんと聞いてくれます。ただし、“事業に対する熱意”と“計画の現実性”は、しっかり伝える必要があります。
面談前に意識したいポイントは以下の通りです。
1. 事業計画書は“自分の言葉”で説明できるようにする
書類が完璧でも、口頭で説明できなければ意味がありません。「なんとなく誰かに作ってもらったな…」と見抜かれてしまうことも。自分の言葉で、どんなビジネスをどう進めていくのかを説明できるようにしておきましょう。
2. お金の話は数字を使って具体的に
「大体こんな感じで…」ではなく、「初月は〇万円の売上、〇万円の経費、利益は〇万円を見込んでいます」と、しっかり数字で伝えることが大切です。返済可能性の根拠にもなります。
3. 自己資金の経緯も説明できるようにする
通帳にあるお金が「どこから、どうやって貯まったのか」は、必ず聞かれます。コツコツ貯金したのか、親族から支援があったのか、ちゃんと説明できるようにしておきましょう。
4. 服装は“清潔感”重視で
スーツでなければダメ、というわけではありませんが、「信頼できる人だな」と思ってもらえるよう、清潔感のある服装を心がけましょう。第一印象も大切なポイントです。
融資面談でのNGワードとは
創業融資の面談で大切なのは、「誠実さ」と「現実的な計画」。
その一方で、うっかり言ってしまうとマイナス印象を与えてしまうNGワードも存在します。
ここでは、実際に面談で避けた方がいい言葉やフレーズをまとめました。
NGワード①「とにかくお金が必要で…」
焦っている気持ちはわかりますが、この言葉は“計画性がない”印象を与えます。
「何に、いくら必要で、それがどう利益につながるのか」を具体的に伝えることが大切です。
NGワード②「たぶん、大丈夫だと思います」
不安を隠そうとして“自信があるふう”に見せようとしても、曖昧な言い方は逆効果。
根拠のある数字や実績をもとに「こういう理由で大丈夫です」と言えるように準備しておきましょう。
NGワード③「知り合いが全部やってくれます」
「他人任せ」の印象になってしまうのも危険。たとえ支援があったとしても、「自分で理解している」「自分で判断している」という姿勢が必要です。
ポイントは、自分の言葉で説明すること、曖昧な表現を避けること。それだけで信用度はぐんとアップします!
どのくらいの融資が妥当?
「希望金額って、どのくらいに設定すればいいんだろう…」
これはほとんどの人が悩むポイントです。
実は創業融資には「これが上限」という明確な基準があるわけではなく、“妥当性”が判断のカギになります。
妥当な金額の考え方は以下の通りです。
- 必要資金の総額
物件費用、設備、仕入れ、人件費、広告費などを合計して、「どれだけかかるのか」を明確に - 自己資金とのバランス
例えば総額600万円かつ自己資金が200万円程なら、融資希望額は400万円が妥当と判断されます - 返済可能性
月々の売上と支出を考慮して、無理なく返済できる金額であるかも重要です
希望金額が高すぎても、「大丈夫かな?」と思われますし、逆に少なすぎると「この人、計画甘いかも」と見られてしまうことも。
「ちゃんと必要な分を、根拠を持って申し込む」これが一番の正解です!
自己資金が少ない場合の対策
「自己資金があまり用意できてない…でも融資を受けたい!」
そんな方でも、対策次第で融資の可能性はグッと高まります。
以下のような工夫をしている人は、審査で好印象を持たれやすいです。
対策① 通帳で“貯金の努力”を見せる
たとえ金額が少なくても、「毎月コツコツ貯めてきました」という履歴があると、信用度が上がります。貯金のペースや頻度は、金融機関にとって重要な判断材料です。
対策② 開業コストを抑える工夫を説明する
たとえば「居抜き物件を活用する」「初期仕入れを少なく抑える」など、工夫してコストを削減している点をアピールすると、堅実な経営姿勢が伝わります。
対策③ 家族や支援者からの協力を明記する
配偶者の協力や、家族からの援助がある場合は、計画の安定性を高める要素になります。無理のない範囲で、サポート体制があることを伝えるのもプラス材料。
対策④ 専門家のサポートを受ける
自己資金が少ない場合でも、事業計画がしっかりしていれば融資が通るケースは多いです。そのために、創業融資に強い税理士や中小企業診断士に相談するのも効果的な一手です。
「自己資金が少ないから無理かも…」とあきらめるのはもったいないです。
大事なのは、「なぜ少ないのか」「それでも成功させるために、どんな工夫をしているか」。そこをしっかり伝えられれば、チャンスは十分にあります!
創業融資はどこに相談できる?相談窓口の選び方
「一人で全部準備するのは不安…」「どこに相談したらいいか分からない…」「面談対策をしたい…」
そんなときこそ、相談窓口をうまく活用するのが成功のカギです!
創業融資に関して相談できる窓口はいくつかあります。以下にそれぞれの特徴をご紹介します。
1. 日本政策金融公庫
「創業融資って、どこに相談すればいいの?」と迷ったら、まず候補に挙がるところが日本政策金融公庫です。創業融資の代表格なので、直接窓口に相談する方も多いです。事業内容や融資希望額などを話すことができます。
でも、「初めてで不安…」「どんな流れなのか分からない…」という方も多いはず。まず最初にやるべきこと、それは相談予約です。「いきなり窓口に行ってもいいの?」と思うかもしれませんが、公庫は基本的に事前予約制。電話やインターネットで予約を取ってからの訪問になります。
予約から相談までの大まかな流れは以下の通りです。
1.近くの日本政策金融公庫の支店を調べる
公庫の公式サイトで、地域ごとの支店一覧が掲載されています。
2.電話またはWebで予約
「創業融資を受けたいのですが、相談したいです」と伝えるだけでOK。担当者が必要な情報を確認してくれます。
3.予約当日、必要資料を持って訪問または電話相談
最近ではコロナ禍の影響もあり、電話やオンラインでの相談も増えています。
この段階では、事業の構想や、必要資金の大まかな内容を話すことになります。準備不足でも相談自体はできますが、ある程度イメージを持っていた方が、アドバイスが的確になるのでオススメです。
2. 地方自治体の商工会議所や産業振興センター
「地元の起業家を応援したい!」というスタンスで、無料相談やセミナーを開催しているところも多いです。地域に根ざした支援が受けられるのが魅力ですね。
制度融資を利用したい場合などは、まずここを訪ねるのが近道です。
3. 税理士・中小企業診断士などの専門家
創業融資に詳しい税理士や中小企業診断士、あるいはファイナンシャルアドバイザーなどに相談すると、より具体的なアドバイスがもらえます。事業計画書のブラッシュアップや、面談対策など、実践的なサポートが受けられるのもポイント。
特に、赤字決算を避けたい方や、創業後の見通しに不安がある方にとっては、こうした専門家のサポートが大きな安心材料になります。
相談先を選ぶときは、「創業融資の実績があるか」「親身に話を聞いてくれるか」が大事なチェックポイント。相談のしやすさや信頼感も大切にしてくださいね。
参考:M&A FAとは?企業買収・合併の専門家が果たす役割とその選定基準|株式会社ファイナンス・プロデュース
よくある質問とその答え
ここでは、日本政策金融公庫の創業融資相談でよくある質問をピックアップして、わかりやすくお答えしていきます!
Q1. 自己資金はいくら必要ですか?
A. 原則として、創業資金の10分の1程度は自己資金が必要とされています。たとえば1,000万円の開業資金なら、100万円程度。ただし、金額よりも「しっかり貯めたか」「計画的に準備しているか」が大事です。
Q2. 赤字になっても融資は受けられますか?
A. 一度でも赤字決算をしていると融資の難易度は上がります。ただし、「なぜ赤字になったのか」「今後どう改善するか」をきちんと説明できれば、可能性がゼロになるわけではありません。むしろ、改善努力を見せることが大事です。
Q3. 開業前でも申し込めますか?
A. はい、創業前でも申し込みは可能です。むしろ「これから開業したい」という人のための制度ですので、タイミングとしては開業準備が整い始めた頃(物件契約前〜直後あたり)がベストです。
Q4. 面談の時間はどれくらい?
A. 通常は30分〜1時間程度。担当者が質問しながら、こちらの事業内容や人柄を確認していくスタイルです。時間内で伝えたいことをきちんとまとめておきましょう。
まとめ
創業融資は、ただ申請するだけではうまくいきません。
事前の準備や面談での伝え方、そして「誰に相談するか」が、成功のカギを握ります。
今回ご紹介したように、日本政策金融公庫をはじめとする公的機関はもちろん、創業融資に詳しい専門家のサポートを受けることで、よりスムーズに、そして確実に融資を実現できる可能性が高まります。
特に「自己資金が少ない」「赤字決算の経験がある」「事業計画に自信がない」…そんな不安を抱えている方こそ、一人で悩まずにプロに相談することが大切です。
熊本を中心に創業支援・融資サポートを行っている当熊本創業融資相談室では、皆様から丁寧にヒアリングさせていただき、事業計画書の作成や融資面談の準備まで、トータルでサポートしています。
相談は無料ですので、まずは気軽にご連絡ください。
あなたの夢の第一歩を、確かなカタチにするお手伝いをいたします!
\お気軽にお問合せください☻/