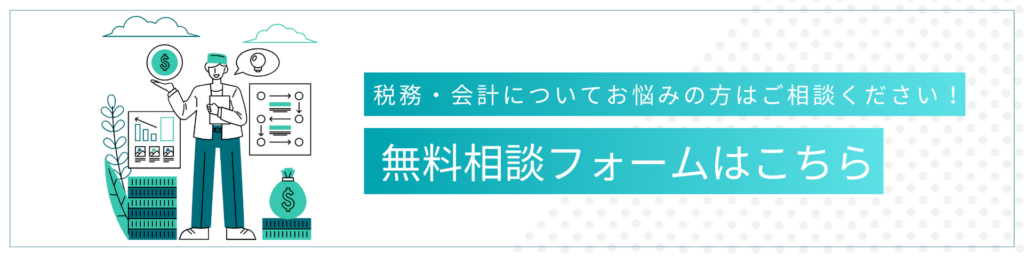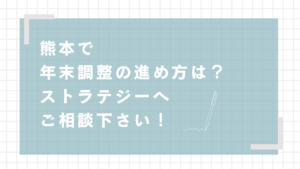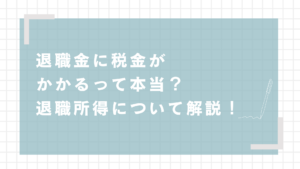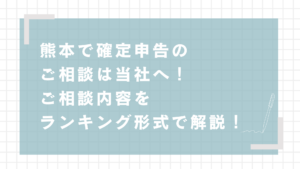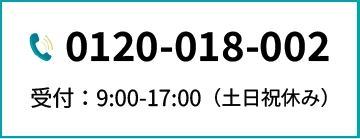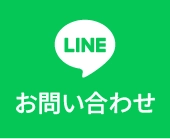年末調整の準備をしましょう!手順やポイントを解説
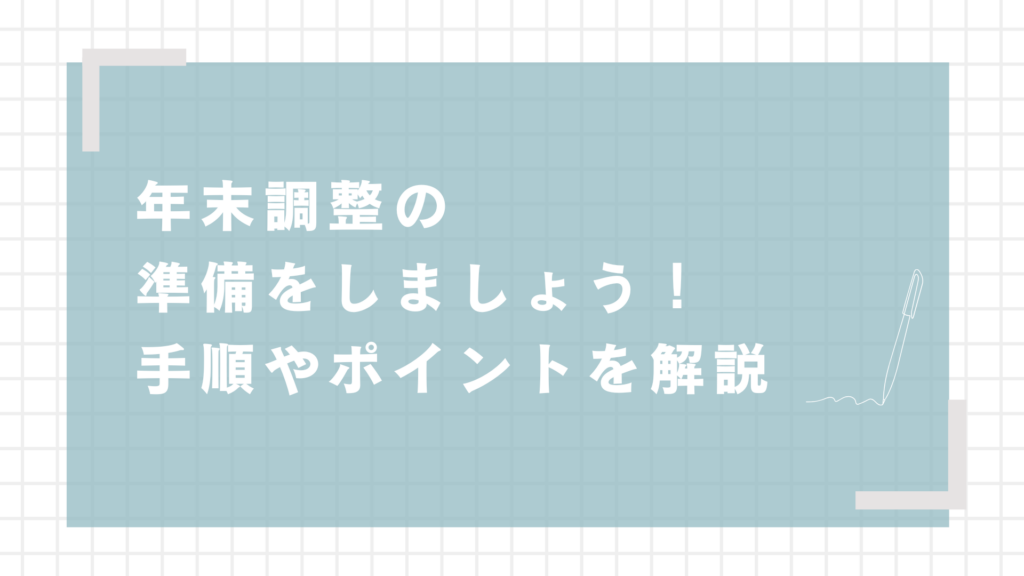
今年も年末調整の季節がもうすぐやってきます。
毎年のことですが、年末調整に扶養控除申告書などの提出期限を厳守してもらったりと、従業員の協力は不可欠です。
そこで本記事では、年末調整のポイントも含め、年末調整を計画的に進めていくための手順やポイントをご紹介します。
\年末調整についてお悩みの方はご相談ください/
無料相談はこちら!
年末調整とは?
事業者に雇用されている従業員、例えばサラリーマンの方は、収入源のほとんどを給与が占めているはずです。
つまり、従業員(サラリーマン)の方の大多数が、この「年末調整」の手続きを通じて、その年に納めるべき所得税(復興特別所得税)を国に納める必要があるのです。
従業員の方は、所得税・住民税、社会保険料等を給与からの天引きで支払っているのが一般的です。
しかし、天引きされる金額はその時点ではあくまで、概算の金額です。
例えば所得税は、累進課税制度が適用されており、一年間の所得に応じて税率(5~45%)が異なります。
つまり、一年度(1月~12月)が終わらなければ、正確な税率や税額は定まらないのです。
そのため、先に概算で所得税が計算され、その金額が給与から天引きされています。
毎年12月末を迎えると、正確な年度の収入が明らかになるため、その後調整することになります。
年末調整は「正確な所得が明らかになったので、概算の金額で天引きしていた税金と実際に支払うべき税金に差異があった場合は、正しい税額に修正しましょう」というものです。
よって、給与天引きで支払った税金よりも実際の納めるべき税金が少ない場合は、払いすぎた税金が戻る=還付されることがあります。
もちろん逆に追加の納税が必要となる場合もありえます。
いずれにしても、正しい税額を納税することが大事なことです。
これが年末調整です。
年末調整の流れ
次に、年末調整の具体的な流れについて見ていきましょう。
以下、流れをまとめました。
- 年末調整用の申告書と必要書類の準備
- 年末調整の知らせと申告書の配布
- 給与等の集計と申告書のチェック
- 年末調整の計算
- 源泉徴収額の納付と翌年の源泉徴収簿の作成
上記3~4の給与の集計や年末調整の計算は、12月末の最後の給与等の支給が決定してから行います。
また、5の源泉徴収額の納付と翌年の源泉徴収簿の作成は、翌年1月の期限以内に行います。
したがって、年内に行える準備は1~2の申告書や必要書類の準備です。
以下は10~11月に準備すべき資料の種類です。
従業員に記入をお願いする資料
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 給与所得者の配偶者特別控除申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書
- 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
提出をお願いする添付資料
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書および借入金残高証明書
- 生命保険料控除および損害保険料控除のはがき
- 社会保険料控除証明書(国民年金のはがきあるいは納付書)
- 前職の源泉徴収票
まとめ
今回は12月に向けた、年末調整の流れと年内に行える準備について紹介しました。
事業主にとっては必須の業務ですが、年に一度しかないため現段階で年末調整の準備を怠っている可能性もあるでしょう。
また、年末調整の取り扱いも毎年改正されるため、しっかりと確認して準備をすることが必要です。
細かい作業ではありますが、今からできる作業をスケジュールと照らし合わせながら進めましょう。
熊本創業融資相談室を運営する税理士法人ストラテジーでは、皆様の年末調整業務も代行させていただいております。
具体的な費用や、不明点等がありましたらお気軽にお問い合わせください!
\お気軽にお問合せください☻/