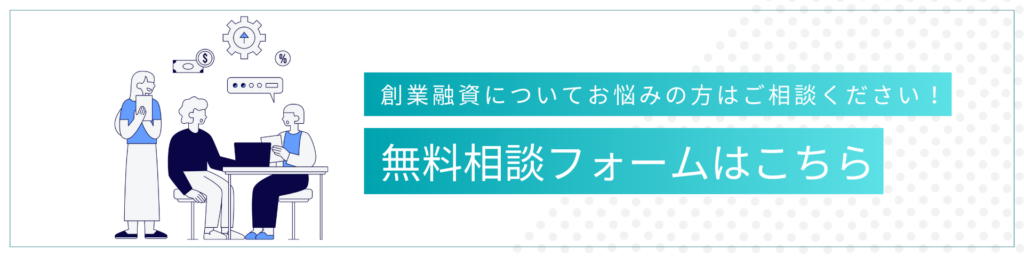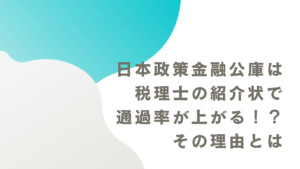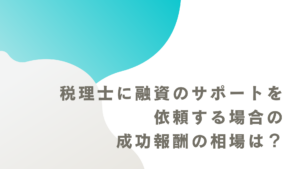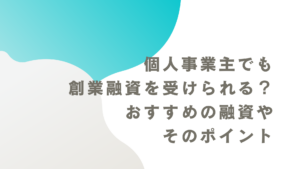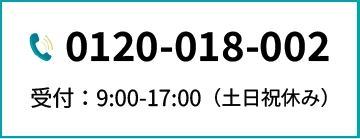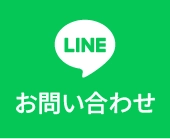日本政策金融公庫で創業融資を受けるときの流れは?必要書類も解説
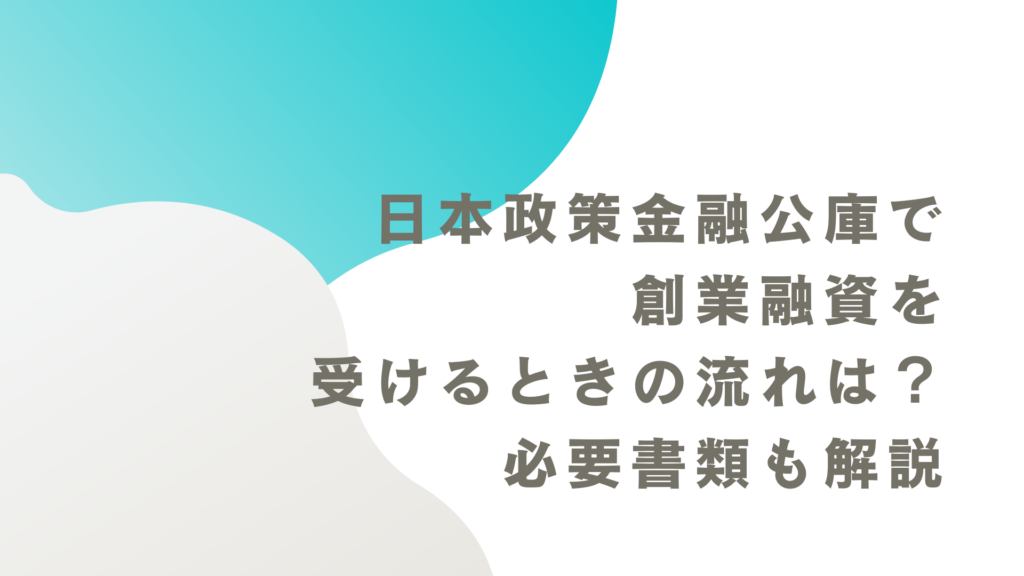
新しく事業を始める際、最も重要なステップの一つが、資金調達です。
自分の貯蓄だけで事業を始めるのは難しい場合が多く、多くの起業家が融資を活用しています。
その中でも、政府が運営する金融機関である「日本政策金融公庫」の創業融資は、特に新規の創業者にとって利用しやすい融資制度です。
民間の金融機関に比べて審査基準が柔軟で、無担保・無保証で融資を受けることができ、事業を始める際の強い味方となります。
本記事では、日本政策金融公庫で創業融資を受ける際の具体的な流れと、必要な書類について詳しく解説します。
これから創業を目指している方や、融資を検討している方はぜひ参考にしてみてくださね!
\創業融資についてお悩みの方はご相談ください/
無料相談はこちら!
創業融資の基本的な流れ
まずは、日本政策金融公庫で創業融資を受ける際の基本的な流れについてお伝えしていきます。
創業融資は、申込から融資までの期間が1ヶ月~最長2ヶ月程度必要といわれており、この期間の流れについて事前に理解しておくことが、スムーズな融資への鍵となるのでチェックしていきましょう!
事前準備
まずは、事業計画書の作成と必要な書類を揃えることが重要です。
融資を受けるためには、事業計画書が審査の鍵となるため、しっかりとした事業計画を立てる必要があります。
必要な書類については相談時や申込時に説明してもらえます。
また、自己資金の額や、それを証明するための書類も必要です。
これらを準備する段階で税理士や専門家のアドバイスを受けることも有効です。
必要な資料については後ほどお伝えします。
融資申し込み
必要書類を揃えたら、日本政策金融公庫の最寄りの支店やオンラインで融資の申込を行います。
申込の際には、事業計画書と共に個人の身元を証明する書類や、過去の収入証明書なども提出する必要があります。
申込時には、一度支店に行くことをおすすめします。
事前に面談場所の雰囲気を見ておくことで、当日の面談の緊張を和らげることができますよ。
面談
融資申し込み後には、担当者との1時間~1時間半程度の面談があります。
この面談は、事業計画書に基づいて事業の内容や将来性、返済能力について話し合う場となります。
具体的な事業の運営方法や、収支の見通し等について説明できるように準備しておきましょう。
そして、どれだけ自分の事業について熱意を持ち、現実的なプランを持っているかをしっかり伝えましょう。
また、面談時の服装ですが、特に決まりはありませんが、最低限のビジネスマナーに沿った服装で臨みましょう。
審査
面談が終わると、次は審査が行われます。
審査時には事業計画の実現性や、返済能力が判断されます。
審査の内容によっては、審査担当者が店舗や事業所予定地等に赴く実地確認があります。
審査期間は申込の条件等によって長くなりますが、基本的に約1〜2週間ほどです。
結果は郵送または電話で通知され、融資が承認されれば契約手続きに進むことができます。
もし、融資が受けられなかった場合は、別の機関での融資を考える必要もあるため、審査が通過しなかった理由をしっかり確認しておきましょう。
融資実行
審査が通過したら、最後は融資を契約を行い、指定した銀行口座に融資金が振り込まれます。
融資が決定した場合は、具体的に以下の書類が必要になります。
審査担当者から説明があるので忘れず用意するようにしましょう。
- 借用証書
- 収入印紙・印鑑証明書
- 預金口座振替利用届
- 送金先口座の預金通帳もしくはコピー
- 包括同意書
- 団体信用生命保険の申込用紙 など
創業融資の申込時に必要な書類には何がある?
融資をスムーズに受けるためには、必要書類の準備が欠かせません。
創業融資を受けるまでの基本的な流れがわかったところで、次は必要な書類について説明します。
創業計画書
創業計画書は、創業融資の審査において最も重要な書類です。
具体的な事業内容や市場分析、収支計画、資金使途などを詳細に記載し、事業は成功する可能性を示す必要があります。
特に、売上見込みや利益予測が現実的であることが求められるため、緻密な計算と準備が不可欠です。
創業計画書を作成する際には、以下のポイントを押さえておくとよいでしょう。
- 事業の概要(何を提供し、どのような価値を顧客に提供するか)
- 市場調査と競合分析(対象市場の規模や、競合他社との差別化要素)
- 収益予測(売上、利益、キャッシュフローの見込み)
- 資金計画(融資をどのように活用し、どのように返済するか)
登記簿謄本や履歴事項全部証明書
初めて日本政策金融公庫から融資を受ける場合には、登記簿謄本や履歴事項全部証明書、日本政策金融公庫所定の起業概要書が必要です。
すでに飲食店等の許認可が必要な事業を営んでいる場合は、許可証や認可証、届出等のコピーも併せて提出しましょう。
創業動機や自己資金の証明
日本政策金融公庫では、創業動機や、創業者がどれだけ強い意欲を持ってその新しい事業に取り組もうとしているかを重視します。
また、自己資金がどれだけあるかも審査のポイントとなります。
自己資金の額によっては、融資の条件が変わる場合もあるため、預金通帳の写しや、過去の資金運用の記録を提出する必要があります。
個人の身分証明書類
融資を申し込む際には、個人を証明するための書類が必要です。
通常は、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどの提示を依頼されます。
また、過去の所得証明や納税証明書も、返済能力を証明するために提出が求められることがあります。
見積書や契約書
事業に使用する設備や物品の購入を計画している場合、見積書や契約書が必要になります。
融資金の使い道を明確にしたり、設備投資の内容や費用を説明するために重要です。
事業に必要な設備や原材料、その他コストが正確に計算されているかどうかも審査の一部となるため、しっかりとした見積書を用意しておきましょう。
提出書類に不備がある場合には、審査に時間がかかる可能性があります。
融資実行までの時間のロスがないよう、提出書類は丁寧に作成するよう心掛けましょう。
日本政策金融公庫の創業融資を成功させるポイント
日本政策金融公庫の創業融資を成功させるためには、いくつか重要なポイントがあります。
事業計画書を充実させる
融資を受けるためには、事業が現実的で実行可能であることが求められます。
事業計画書では、そのことを具体的に表記しなければなりません。
市場調査や競合分析がしっかり行われており、ターゲットの顧客に対して確実に価値を提供できる事業計画が立てられているかどうかが審査の対象となります。
特に、売上見込や利益予測が無理のない範囲で設定されていることが重要です。
過度に楽観的な予測ではなく、堅実な計画を立てることが、審査の通過に繋がります。
また、事業計画書では、将来的な事業展開のビジョンも含めて記載すると、審査担当者に対して説得力が増します。
例えば、2年後や3年後の売上予測や、マーケティング戦略、成長の見込についても触れることで、信頼性の高い計画書になります。
自己資金を増やしておく
融資の際に自己資金が多いほど、審査では有利になります。
一般的には事業計画書に記載された総資金の3分の1程度を自己資金として持っていることが望ましいとされています。
自己資金が少ない場合は、創業計画書を充実させたり、自己資金が少ない理由や代替手段についても説明できる準備が必要です。
また、自己資金は預金通帳や銀行取引の記録で証明する必要があるため、日頃から計画的に資金を管理し、見せられる形で蓄えておくことが大切です。
面談での準備を怠らない
融資の面談は、審査の重要なプロセスです。
担当者に対して自分の事業計画やビジョンをわかりやすく伝えることができるかがポイントです。
自分の事業に対する熱意や意欲をしっかりと伝えましょう。
面談前には、事業計画書に記載した内容を再確認し、具体的な数字やビジネスの運営方法について明確に応えられるように準備をしておきましょう。
担当者からの追加の質問や不明点が尋ねられることがあるため、どのような質問が来ても対応できるように、柔軟な対応力も求められます。
信用情報を確認しておく
融資の審査では、創業者の信用情報もチェックされます。
過去にクレジットカードやローンの返済で問題があった場合、それが審査に影響を与えることがあります。
事前に自身の信用情報を確認し、問題がないかどうかを確認しておくことが大切です。
株式会社シー・アイ・シー(CIC)や、株式会社日本信用情報機構(略称 : JICC)で調べることができます。
返済計画を現実的に立てる
融資を受けた後、返済をスムーズに進めるためには、先述の通り、現実的な返済計画を立てることが必要です。
事業の収益予測を基に、無理のない範囲での返済スケジュールを設定し、事業の成長とともに計画を見直していく柔軟性も持っておくと良いでしょう。
創業者の経験やスキル
創業者がそのビジネスに関連する経験やスキルを持っているかも、審査のポイントになります。
例えば、飲食店を開業する場合、過去に飲食業界での勤務経験があると有利です。
また、特定の業種で必要な資格や免許を持っている場合も評価されるため、これらの情報を事業計画書に記載することが重要です。
創業融資の活用方法と注意点
融資を受けたことは、事業のスタートラインに立ったに過ぎません。
その資金をどのように活用するかが、事業の成功への大きな要となります。
次に、創業融資を受けた後に押さえておくべき重要なポイントについて解説します。
資金の使い道を明確にする
融資金は、事業に必要な資金として活用するために、具体的な使い道を明確にしておくことが大切です。
例えば、事業に必要な設備や材料の購入、人件費、広告宣伝費等、事業の成長に直接貢献する分野に投資することが多いです。
資金の流れを把握し、無駄遣いを防ぐために定期的に予算を見直し、経費のコントロールを行うことが必要です。
私的な用途に資金を流用することは絶対に避け、事業の透明性を保つことを心掛けましょう。
キャッシュフローの管理
事業に軌道を乗せるためには、安定したキャッシュフローの確保が重要です。
融資を受けた後も、計画的に資金を運用し、売上と経費のバランスを保つことで、事業を継続的に成長させることができます。
特に創業したばかりの時は、予期せぬ出費が発生したり、予想以上に資金が必要となることが多いため、資金繰りの見通しを慎重に立てておく必要があります。
また、事業の成長に応じて追加の資金が必要になる場合もありますよね。
その際は再度融資を検討したり、事業収支の再投資などを検討しましょう。
返済計画の見直し
融資を受けた後は、返済計画をしっかりと立てておくことが重要です。
無理のない範囲で、事業を安定して運営していきたいですよね。
日本政策金融公庫の融資は、金利が低く返済期間も比較的長いため、資金管理さえ適切に行えば、返済は無理なく進められます。
しかし、事業の進展状況に応じて、この計画を定期的に見直すことも重要です。
例えば、事業が順調に進んでいれば、返済期間を短縮することも可能ですし、逆に予想外のトラブルが発生した場合は、返済条件の見直しを検討することもあります。
日本政策金融公庫では、予定通りの返済が難しい感じた場合、柔軟な対応が可能なケースもあるため、早めに相談することをお勧めします。
融資を受けた後も、日本政策金融公庫への相談は可能ですので、定期的に状況を報告し、必要に応じてアドバイスを受けると良いでしょう。
また、創業融資を受ける際や、融資決定後の資金運用については、事業運営に必要な知識や経験を持っている税理士や経営コンサルタント等の専門家のアドバイスを活用する方法もあります。
専門家に適切なアドバイスを受けることで、融資を有効に活用できる可能性が高められます。
まとめ
日本政策金融公庫の創業融資は、新しく事業を始める方にとって非常に心強い資金調達方法です。
その融資を成功させるためには、事業計画書の充実、自己資金の確保、面談でのアピール、そして現実的な返済計画を立てるなどのしっかりとした準備と計画が必要です。
さらに、融資を受けた後も、資金を適切に運用し、キャッシュフローの管理や事業の成長を見据えた計画を進めることが重要です。
熊本創業融資相談室を運営する税理士法人ストラテジーでは、そのような事業計画書の作成方法や面談のアドバイスはもちろん、具体的な資金運用の方法や返済計画についてもアドバイスさせていただいております。
ご相談は初回無料で行っております!
日本政策金融公庫からの創業融資を検討されている方は、以下ボタンよりぜひお気軽にお問い合わせくださいませ!
\お気軽にお問合せください☻/